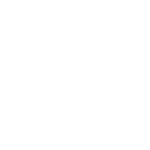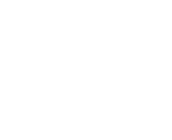おだかの「天の虫」を追って。【前編】
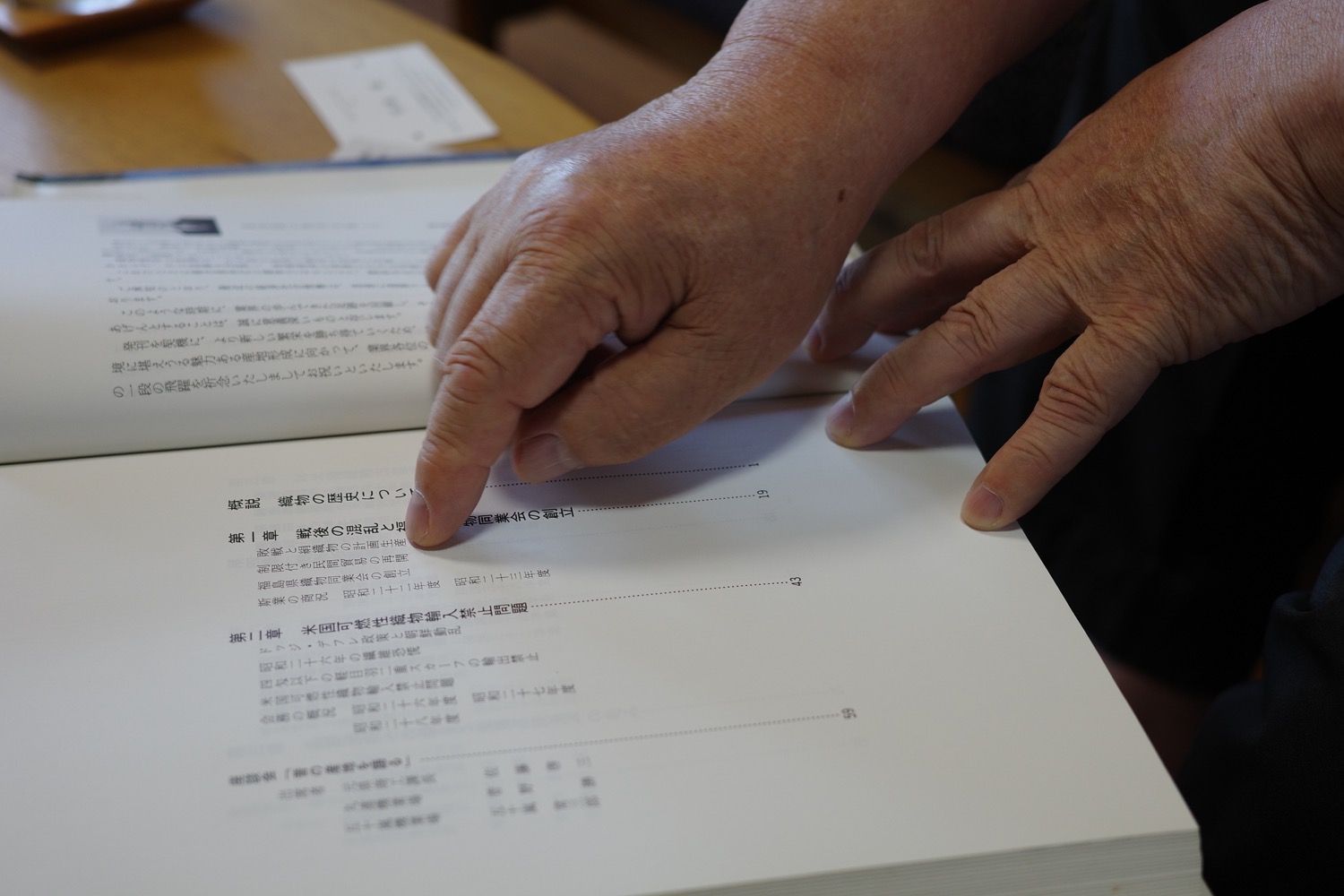
かつて小高区で盛んだった養蚕業の歴史・文化を守り、未来へ繋げていくために、養蚕にかかわりのある方々の元を訪ね、貴重な声を紡ぐシリーズ。前編では農家の根本さんご夫婦、機織り工場を営んでいた和田さんにお話を伺いました。
“蚕さま”と暮らした、根本さんご夫婦のお話
明治時代、「軽目羽二重」の産地として知られ、“絹織物の里”と呼ばれた小高区。その絹糸をつくるため、小高の多くの農家が養蚕を行っていました。しかし、安価な海外産の糸の輸入や和装需要の減退など、時代の移り変わりと共に養蚕業は衰退の一途を辿ることに。
その歴史の中でも、約20年前まで養蚕を手掛けていたというのが、農家の根本さんご夫婦。築60年というご自宅にお邪魔して蚕のことを伺うと、二人ともやさしい表情を見せながら、当時のことを振り返ってくれました。

——小高には養蚕農家の方がたくさんいたと聞きました。
幸子さん この集落には40軒くらい農家がいたんだけど、20軒くらいは“蚕さま”を飼っててね。
幸子さんが自然と口にした「蚕さま」という言葉。養蚕が盛んだった地域では親しみや感謝の気持ちを込め、蚕のことを「お蚕さま」などと呼んでいたそう。一般的に養蚕農家は米などの主要農産物の閑散期などを活用し、餌となる桑の栽培・刈り取り、蚕の飼育、繭の収穫を行い、製糸会社に納めていました。
——蚕“さま”なんですね。
幸子さん そうですねえ。家計を支えてもらったし、ありがたい存在で。蚕さまに朝ご飯をあげてから、私たちのご飯を用意したり。至れり尽くせりで、お客様や神様みたいだったね。

——どれくらい前から蚕を飼っていたんですか?
洸一さん もう俺の5代くらい前からはやってたんでねえかな。もう、他の人たちが養蚕をやめた1990年まで続けて。戦時中も軍の指示で周りが食料を優先する中、小高ではうちともう1軒だけが落下傘を作るために養蚕をしていたんだ。
——戦時中も。長い期間、養蚕をしていたんですね。
洸一さん うちは小高でも、かなり大規模な養蚕農家だったから。蚕の餌にする桑畑が2.5haあって、繭は年間2トン納めてたね。
幸子さん 100万匹以上は飼ってたよね?普通の農家は蚕屋(かいこや)っていう、蚕を育てる場所だけなんだけどね、うちはそれじゃ足りないから、家の中でも飼ってたの。私たちの布団も蚕さまに囲まれて、ガサガサ動く音がする中で寝てたんですよ(笑)。

——想像すると、すごい光景(笑)。本当に蚕と一緒に暮らしていたんですね。
洸一さん そうそう。いい繭をつくってもらうためには、蚕さまに気持ちよく過ごしてもらわないといけないから。栄養のある桑を育てて、部屋の温度や湿度も管理してね。そのために、この家は天井を低くしてあるんだよ。
幸子さん 冬はここにあった囲炉裏で炭焼きして、蚕さまのために部屋をあたたかくしてね。夜もつきっきりで火の番をしたりして。
家の設計まで、蚕のことを考えていたという根本さんのご自宅では、1階を蚕の飼育場、2階を繭を吐き出す場にしていたそう。話が一段落すると洸一さんは「ちょっとそっち行ってみるか」と隣の部屋へ案内してくれました。


洸一さん 天井に何カ所か2つ凹みがある板が取り付けられてるでしょう。これは蚕を育てるための棚を組んでいた跡だね。
幸子さん こう見ると、この家も蚕屋のまんまだねえ。
実際に蚕を育てていたお二人の飾らない言葉や建物に残る痕跡に、小高の農家の方々と養蚕の密接な暮らしが、そこに確かにあったことを肌で感じることができました。
「町中から機織りの音が」。地域で支え合った小高の織物業
続いて、お邪魔したのは3年前まで機織り工場「和田善行機業場」を営んでいた和田善行さんのご自宅。広い敷地には2棟あった工場のうち、1棟が今も残っています。

「うちに届く頃には糸になっているし、俺が会社に入った頃はもう養蚕はほとんど行われていなかったから、あまり蚕の記憶はないんだよね」と語る和田さん。しかし、そのお話から、織物産地としての小高の情景が浮かび上がってきました。
——和田さんの工場では、いつ頃から機織りをしていたんですか?
和田さん “機屋(はたや)”を始めたのは祖父の代からだね。俺は東京の商社から戻って、仕事を始めたのが26歳の時。だから……1973年。その頃には蚕の絹糸は、高級品でしか使われなくなっていたね。
——ただ、小高には機織りの工場がいっぱいあったんですよね?
和田さん 子どもの頃から、町にいて機織りの音が聞こえない場所がなかったね。朝から晩まで「ガチャン ガチャン」って。

取材時に和田さんが見せてくれた資料によると、小高には1974年の時点で44軒の機織り工場があったと記録されています。小高は川俣、飯野とともに福島県における織物の三大産地の一つ。和田さんは「織物がこの町をつくったのは間違いないな。小高は機屋の町だったと俺は思ってるよ」と力強く言い切りました。
——小高ならではの特徴とかはあったんですか?
和田さん 川俣や飯野に比べると、小高は一つひとつの工場が小さくてね。だから「相馬絹業協働組合」という組織をつくって、そこにすべての仕事を集約して。みんなで協力していたのが強みだね。小学校の向かいに事務所があって、子どもの頃、野球をしているとそこで働いている人が声をかけてくれたりして、織物やそれを生業にしている人たちが自然と身近な存在になっていたな。
——小規模な工場が多い小高だったからこそ、一致団結していたと。
和田さん そう。東京の大手メーカーの取引も組合だったからこそ、受けられたし。それこそ親戚よりも助け合ってたな。
——親戚よりも。
和田さん 俺が小高に戻ってきた3カ月後に父親が心筋梗塞になって倒れちゃったんだけど、右も左も分からない自分に、他の工場の人たちが毎日交代で仕事を教えにきてくれてね。本当に支えてもらったんだ。
——なかなかできることではないですよね。
和田さん そのおかげで、うちは小高で最後の1軒になるまで機屋ができたんだ。


和田善行機業場は2020年に閉鎖。和田さんは、中ががらんと空いた工場へ案内してくれました。
和田さん 震災前には7、8軒になって、最後がうちになったけどね。くさいこと言うと親父には「最後の一軒になるまで続けるから」と事あるごとに話してたんだ。
——その約束は果たせましたね。
和田さん うん。機屋として悔いはないな。

前編では根本さんご夫婦、和田さんに、これまでの小高の養蚕や織物について伺いましたが、その歴史の糸は今も途切れていません。
後編では、小高で育てた蚕の絹糸でアクセサリーなどを作っているNPO法人「浮船の里」の島抜さんに、絹糸の魅力や活動する理由についてお話を伺う予定です。