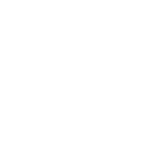農業で実り豊かな未来を。小高に開校!『みらい農業学校』におじゃましました。

2024年4月、小高区南鳩原(みなみはつぱら)に開校した「みらい農業学校」。なぜいま、小高で農業なのでしょうか。地域が持つ農業の課題や、可能性、そして校名のとおりどんな「未来」へ進もうとしているのか、学校を運営する株式会社マイファームの新開さんにお話を伺いました。
「自産自消」で、もっと人と農がつながる世の中へ。
今回学校を代表して取材に応じてくださったのは、みらい農業学校を運営する株式会社マイファームの社員であり、学校が入る「みらい農業交流スペースTSUMUGI」に常駐する新開春美さんです。

——本日はよろしくお願いします!
新開さん よろしくお願いします。
——早速ですが、この学校は建物も庭もかわいらしいですね。
新開さん はい。もともと幼稚園だった建物をリノベーションし、2024年4月に「みらい農業交流スペースTSUMUGI」としてオープンしました。みらい農業学校は、その施設を利用して講義をおこなっています。

——-農業学校というもの自体が珍しいと思うのですが、まずはマイファームさんがどんな会社か教えていただけますか。
新開さん わたしたちマイファームは、「自産自消」という理念のもと「人と農のつながりをつくる」ための企業です。
——-「自産自消」ですか?
新開さん はい。自分の手で耕し、育て、食べる。人と自然の関係をより豊かにしたい、という考えです。もともとは、弊社の代表が全国で増加する耕作放棄地を問題視し、自分も農業に参画しようとしたことが会社創設のきっかけです。しかし、いざ農業を始めようとすると耕作放棄地はたくさんあるのに、個人が農地を手に入れるためには、農地の価格や既存のルールなど、とても高いハードルがあることに気が付いたんです。

——-従来の農業の仕組みが、壁になってしまったのですね。
新開さん そうなんです。だからこそ、より多くの人が農業に参加できる体験農園づくりを始めました。それが、弊社の取り組みのスタートです。自分が食べる作物を自分で育てる経験を通して、自然の中で自分が生かされる楽しさを感じる場所を目指しました。私自身、スーパーに売ってあるものを買って食べて、おなかは満たされるけれど、心は満たされないなと常々思っているんです。
——なるほど、それが「自産自消」の理念で、“心も満たされる農業”を目指した活動が始まっていくのですね。
新開さん マイファームでは、このみらい農業学校のほかにも、仕事をしながら農業を週末に学ぶ社会人向けの「アグリイノベーション大学校」(横浜、千葉、埼玉、大阪、京都)や、有機農業の教育に特化した学校として「丹波市立農(みのり)の学校」(兵庫県)などを運営しています。
小高だから生まれた農業学校。
そんなマイファームが、新しい学校を小高に開いたのは、どのような背景があるのか、伺ってみました。
——-南相馬や小高の農業にはどういった特徴があるんですか。
新開さん まずは、日本の農業全体について話したいのですが、やはり担い手不足が深刻な状況です。サラリーマンだった人がなんの勉強もせずいきなり農業法人に就職して、ギャップを感じてすぐに辞めてしまう、なんてケースも多いです。
——農業での働き方には、どのような形態があるのでしょうか?
新開さん 農業は 個人事業主である「独立就農」と営農法人などに雇用され安定収入が見込める「雇用就農」の大きく 2つに分かれます。雇用就農は農業を行う社員として、その法人に就職するようなイメージです。実は、南相馬市では震災以降、急激に農業の法人化が進んでいるんです。法人化すると農業用機械やスマート農業を取り入れる体制などを整えることができます。
——-人の力を補う工夫が進んでいるのですね。
新開さん そうですね。そして人手が少ないということは、今いる人たちで力を合わせてやっていく必要があるということです。さらにみんなで協力していく雰囲気を育めればと思います。農業法人化が進む南相馬、小高の地域性と私たちのビジョンの一致が、この地域に開校した最も大きな理由です。
——ここからは学校について具体的にお伺いしたいと思います。どんな特色を持った学校なのでしょうか?
新開さん いちばんの特色は、先ほどご説明した「雇用就農」に特化したカリキュラムであることです。農業の法人化が進んでいるこの地域の現状と、物価高騰の情勢なども影響して、新規で農業を始めることが難しくなっています。おおよそですが20年くらい前にくらべて初期投資に3倍以上のコストがかかるようになってしまいました。
——-え!せっかくやりたかった農業を始める際に、大きなリスクを背負うのはとても不安ですね…。
新開さん そうなんです。なのでみらい農業学校では雇用就農を薦めています。特に新規で農業を始める方にとって、いきなり独立するのではなく農業法人に就職し、この地域の農業を学ぶというのも、とてもいい選択肢だと考えています。
——-やってみて自分に合えばそのまま法人で働いて、いずれ独立することもできますもんね。
新開さん そうですね。まずは農業で働く入り口として、法人に就職することがひとつの安心材料になるのではないかと思います。入学するために遠くから移住してきた方も、農業を学びながら、この地域の良さも知っていける。そんな方たちと、この小高や南相馬、ひいては浜通り全体の農業を盛り上げていきたいですね。

——-そのほかに学校として特徴的な部分はありますか?
新開さん 農業の経営視点を身につけられるところでしょうか。将来、雇用就農でも独立就農でも、経営の視点というのは必要になります。この学校でしっかりと知識を培って、活躍してもらいたいです。
——-農業を仕事にすることを目指す受講生さんたちにとって、とても大切なことですね。みなさん、卒業後の進路は別々なんですよね。
新開さん そうですね。でもこの学校は卒業したら終わり、というわけではありません。そこが、この学校のとても良いところだと思うのですが、1年間の学びを通して育んだ仲間のつながりは、就農した後も地域の中で生き続けると思います。また、ここは「みらい農業交流スペース」ですので、農業で相談したいことがあれば誰でも訪ねてもらえるような場所にしたいんです。
様々な気象条件や、生きものである作物を相手にする農業を1年間で学びきることは不可能。そこは、「交流施設」という側面を活かして卒業後もいつでも学び直しに訪れてほしい、と新開さんはおっしゃいます。
新開さん 農業って、周りの意見を聴くことがとても大切なんです。例えば「うちの畑でこんな病気が出ているよ」とか「そっちの作物の調子はどう?」とか。そういう情報交換ができることって、本当に有意義なんです。将来的にこの地域の農業の盛り上げるためにも、人と人のつながりを大切にしたいですね。
——-知らない地域の中で、関係値をイチからつくり上げるのは、なかなか難しいですよね。小高の農家さんから、震災後に一番しんどかったのは「周りにコミュニケーションがとれる農業仲間がいなくなったこと」と聞いたことがあります。
新開さん そのような状況を避けるためにも、農業のコミュニティーをどんどん広げられると良いですよね。
みらい農業学校が目指すゴールとは。
——では、そんな特徴的なカリキュラムを持ったみらい農業学校が、農業を行う上で大切にしていきたいのは、どんなことですか?

新開さん いちばんは「農業を楽しむ」という気持ちでしょうか。現状、農業には難しい課題がありますが、おもしろい部分もたくさんあるんです。楽しむためには、やっぱり人手が必要ですから、「地域を担う」人材になることも目標にしてもらいたいです。
——-農業で地域を担うとは、具体的にどんな状況でしょうか?
新開さん この地域の農家さんたちは、みなさん「より良い農業のために、アレがあったらな」と少し足りない部分を抱えている、という状況だと思います。私自身も、この学校としても、そのリクエストに応えるアプローチをしていきたいと考えています。
——-常に“お題”がある状況なのですね。
新開さん はい。そういう環境って大事だと思うんです。自分が、そのお題に応えるための力を鍛えたら、相手や地域の役に立てる。人に喜んでもらえるって、とても心も満たされることだと思いますね。
——-マイファームさんとして大切にされている“心も満たされる農業”にもつながりそうですね。
新開さん そうですね!受講生のみなさんにも、1年間の学びの中で「こんな風に地域の役に立ちたい!」という想いを見つけてもらいたいです。卒業後に農作業を通して地域の力になれれば、その方自身も楽しい、作物や自然も育って楽しい、という良い循環が生まれていくと思います。
「農業から生まれるコミュニケーションが、良い」齋藤志真さん

そして今回はみらい農業学校に通う受講生2名にインタビューをさせていただきました。1期生は全員で15名。年齢や出身などもバラバラで、みなさん「農業をしたい」という想いのもと小高に集まっています。最初にお話を伺ったのは、1期生の中でいちばん若い20歳の齋藤志真(さいとうしいま)さんです。
——-農業をやってみようと思ったきっかけはなんですか?
齋藤さん 自分は大学3年の年なんですけど、就活も始まってきちゃうので、その前になにかやりたいことにチャレンジしようと思っていました。ちょうどそんな時、大学のボランティアセンターで「とうきょう援農ボランティア」※という取り組みを見つけたんです。
※「とうきょう援農ボランティア」は、人手不足で困りごとのある農家と、農業に興味がある一般のボランティアをつなぐ事業。
——-農業にふれたのは、それが初めてですか?
齋藤さん ほぼそうですね。すごく楽しかったです。前から、デスクワークとかはしたくないなと思っていて。
——-農業のどんな部分が楽しかったのでしょうか?
齋藤さん 僕たちくらいの世代ってデジタルと一緒に生活してきたから、自然と向き合うってことが、まず新鮮でした。あとは、援農ボランティアで家族経営の農家さんのお手伝いに行ったのですが、3時のお茶タイムにゆっくり話したり、隣の畑の人と交流する時間があったり。農業から生まれるコミュニケーションが、すごく良いなって感じました。

——-一緒に農業に向き合うことで、人の関係も深まっていく、という感じでしょうか?
齋藤さん そうですね。だから小高でも、学校で農業の勉強に向き合うことはもちろん、もっと人とコミュニケーションをとって、地域の人と仲良くなりたい。農業に関わらず、関係の輪を広げていきたいです!
「経歴を生かして、地元の農業のはたらき方を変えたい」但野陵子さん
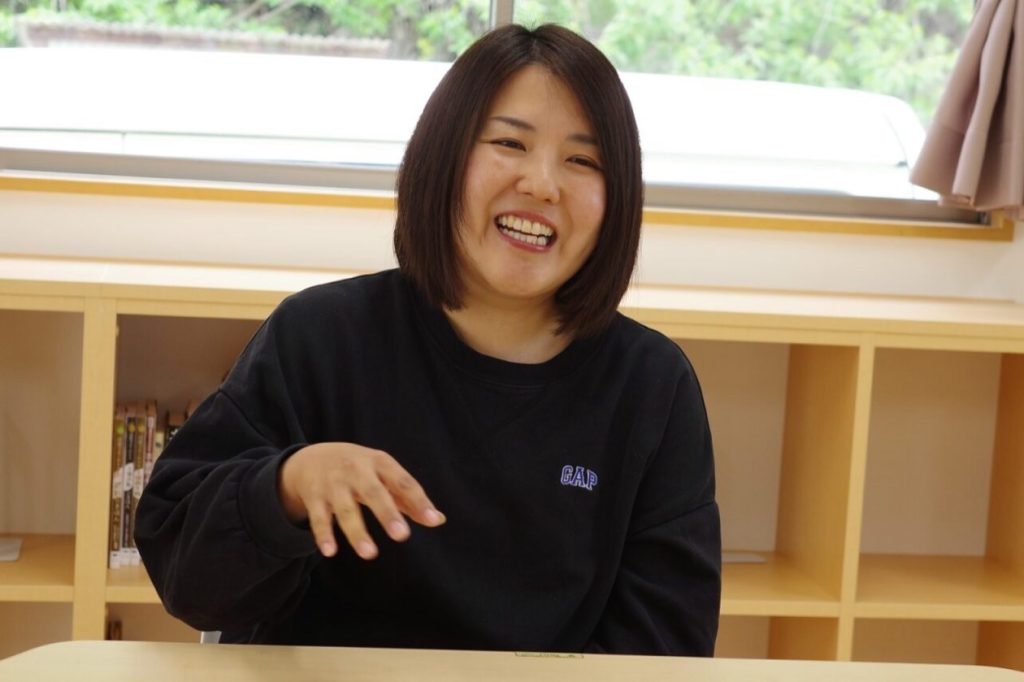
次にインタビューに応じてくださったのは、前職では農業と全く違うことをされていたという但野陵子(ただのりょうこ)さんです。
——但野さんが農業を志したきっかけは、なんだったのでしょうか?
但野さん もともと東京でITツールの導入支援やシステムエンジニア、カスタマーサポートなどをやっていました。その中で「もっと働き方の改善などに直接影響を与えられえることがしたい」と思いました。もともと、実家のある福島に移住しようとは考えていて。農業や漁業をもう一度盛り上げようとする福島県の姿を見て、農業に取り組んでみようと思ったんです。自然が好きでもあったので。
——-これからどんな農業をされていきたいか、具体的に決まっていらっしゃるんでしょうか?
但野さん これまでの職で培ってきたIT関係のスキルを活かして、スマート農業などの普及に貢献したいという想いがありつつ、独立して農業をやってみようかなとも思っています。作物を6次化して実際に販売までやってみたいという希望もあるんです。

——-1年間の中で、どんどん具体化できると良いですね。最後に、学校生活はいかがですか?
但野さん 受講生は、年代もやりたいことも違うんですけど、上下関係がなく対等で、みんな学生として横一列のスタートをきれる空気感がとてもいいなと感じています。将来、自分が会社やグループをつくる時には「こんな雰囲気を手本にしたいな」と思ったりもしています。
農業の未来に向かって、はじまる学び。
最後に、授業の様子やこれからのカリキュラムについて教えていただきました。
新開さん 学校の専任講師は、小高区泉沢地区で実際の農業や農業指導経験を持つ遠藤先生にご担当いただいています。また外部講師による教育もとても充実しているんですよ。
——-どのような方たちでしょうか?
新開さん たとえば、農業機械メーカーと提携して農機具の安全な使い方を学ぶ授業をしていただく予定です。そのほかに地元の農業法人にも、研修授業などにご協力いただけないか相談中です。リアルな働き方を在学中に知っておくことで、地域への理解や卒業後の選択肢が増えることにつながると考えています。

——-夏に向けて収穫も増えていきそうですね。
新開さん そうですね。きゅうりやトマトなど、夏に向けて作付けしている野菜たちがどんどん収穫時期を迎えていきます。学校には、授業で使うほ場のほかにも、受講生の方たちが自由に野菜を育てられる広い畑があるんです。みなさん思い思いの作物を育てていて、収穫の時期が楽しみです。


——改めて、最後にお伺いしますが、この学校をどのように運営していきたいですか?
新開さん まずは、小高のみなさんにこの学校のことを知ってもらいたいですね。この畑で採れる野菜を使って、誰でも参加できる試食会や販売会などのイベントも企画していく予定なんです。
ワクワクした様子でそう語る新開さん。地域の農業を守り、いっそう盛り上げていこうとする想いと、全国から集まった農業を志すみなさんの新しい力が出会うみらい農業学校。
農業を軸に、携わる人の想いや地域を紡ぐ新しいコミュニティーの形は、小高だけでなく日本の農業の未来にとって、様々な課題を解決する光となるのではないでしょうか。
〈みらい農業学校の情報はこちらから〉
\第二期生募集は夏頃に開始予定です。HP、各種SNSでお知らせします/
Web: https://agri-innovation.jp/mirai/
instagram: https://www.instagram.com/minamisoma_mirai_agri/
note:https://note.com/minamisoma_mirai