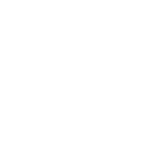小高で見つけた、輝ける場所。

陽の光にあたり、キラキラと輝くガラス細工。どれも繊細で技巧が凝らされているが、決して飾らない、まっすぐな印象がある。なんとなく、小高を象徴しているような気もする。
ガラス細工の名は『iriser -イリゼ-』。小高で暮らす女性たちが一つ一つ手作業でつくる、ハンドメイドのアクセサリーブランドだ。

このイリゼの広報やブランディングを担当しているのは、地元・小高区出身の根本李安奈さん。2021年の2月に東京から小高に帰ってきた26歳の若者だ。
「今の小高は、以前暮らしていた時の小高とは違うものだと思ってます。地元の同級生にも、この小高で楽しんでいる自分を伝えたい。」という根本さん。
“新天地”小高の舞台で、凛と輝く根本さんにお話を伺ってきた。

ずっとやりたかった、「地域を伝える仕事」を小高で。
根本さんは現在、小高区を拠点に若者の起業支援や働く場の創出を事業とする株式会社小高ワーカーズベース(以下、OWB)の職員として働いている。イリゼはこのOWBが手がける数々の事業のうちの一つとなっている。

イリゼのガラスアクセサリーは小高で暮らす女性たちの手によって作られる。OWBは若者や女性にとって魅力的な職場を地域に作ろうと、耐熱ガラスメーカーのHARIOと提携し、2015年に『HARIOランプファクトリー小高』を設立。イリゼはここから生まれたブランドだ。
フランス語で「虹色に輝く」を意味する”iriser”。アクセサリーを身につける人と、作り出す人、それぞれが虹色に輝けるように。そんな願いを込めて名付けられたという。
「子どもがまだ小さい親世代や、介護が必要な家族がいる方でも、自由に働き方が選べる職場になっています。」と根本さん。確かにお昼ごろ行われた取材中にも、常に出勤する人、退勤する人、それぞれの人の出入りがある様子だった。また、働く人の年齢もさまざま。自由で多様な、魅力ある職場が作り上げられている。

根本さんはイリゼの他にも、若者の起業支援プロジェクト『Next Action → Social Academia Project (通称NA→SAプロジェクト)』の事務局の業務も担当している。

「もともと地域を伝える仕事をしたくて、東京で広告の会社に勤めていました。いまは東京で積み重ねてきたスキルを生かしながら、小高で働いています。」
小高で自分のやりたいことを実現している根本さん。だが、そもそも根本さんはなぜ新天地を小高の場に求めたのだろうか。
東京にずっといても、オリジナリティは生まれない。
「東京では3年間社会人やってたんですけど、コロナ禍になって”東京にいるのつまんないな”ってなっちゃって(笑)。それでまずはどこでもいいからとにかく地方に行こうと思ったんです。」
コロナ禍の中で、根本さんは自分が東京にいることにだんだん疑問を持つようになっていった。

「東京でみんなと同じようなことをしても、雇う側にとって使いやすい人材にはなるのかもしれないけど、オリジナリティはないなって。終身雇用がリアルじゃない私たちの世代にとって、例え失敗しても地方で何かやってみるっていうのは全然リスクではないなと。」
根本さんにとって、小高は”愛する地元”というより”挑戦の場”であるという。
震災後、原発事故による避難指示の期間を経て、小高区では新たなプロジェクトや施設が次々と誕生した。その核となったのが、根本さんが働くOWB。このOWBの数々の事業を目当てに、全国各地から小高に若者が集まってきている。根本さんもその中の一人だ。
根本さんは全国各地から新たな活躍の場を探していたが、OWBが南相馬市と共同で手がける、起業支援プログラム『Next Commons Lab 南相馬』を見つけたことで、小高に興味を持つようになった。実際に説明会まで足を運び、代表の和田智行さんと話をする中で、OWBへの参加が決まった。
来るべき”10年後”のために、自分を積み重ねてきた。
小高区はほぼ全域が福島第一原発から20km圏内に位置し、震災後、街から人の姿が消えた。ふるさとに戻れるのは10年後になるかもしれないという報道もあった。実際には避難指示は震災から5年後の2016年に解除されたが、今でも「中学校の同級生で帰ってきてるのは一人だけ」という状況だ。
「震災直後は故郷を奪われた気がして、その気持ちを原動力に動いていた時もあった。」と根本さんはいう。しばらく地元に戻れないことを覚悟しつつも、10年後にふるさとへ戻れるその日に何かできるようになっていたいという想いのもと、東京の芸術系の大学へ進学する。
「当時、映画に興味があって。それに映画を作ればロケ隊も来るし、ロケ地を巡りに観光客も訪れるようになるから、監督になって地元で撮影をすればこの地域が潤うんじゃないかと思って映像系の学科に入りました。」
「ただ、次第に映画監督はロケ地を選べないということがわかってきて(笑)。本当に自分がやりたいことってなんだろうと考えたら、映画を撮るというよりも、その地域を伝えるということだったのかなと思ってきたんです。」

大学を卒業したのち、根本さんは東京都内の広告会社に勤めることになる。
「自分が地元に直接できることはないなと思いながら、それでも東京で力をつけておけばいつか発揮できる時が来るんじゃないかと思って広告の仕事をしてました。」
はっきりと言葉にはしなかったけれども、根本さんの心の中には常に小高への想いがあるように感じられた。
課題先進地だからこそ、ここで培ったことはどこでも通用する。
小高区は2016年の避難指示の解除から5年あまりしか経っていない。震災前は、約13,000人の住民が暮らしていたが、今は、約3,800人の住民が暮らしている。
「小高の課題はどこに行っても普遍的な課題だと思っていたので、そういう意味もあって数ある地域の中からあえて地元である小高を選んで帰ってきました。ここでやれるなら、どこでも通用すると思って。」
たしかに、小高が抱える課題は全国どの地域でも共通することだ。少子高齢化、人口減少、商業の空洞化など… しかも、小高では他のどの地域よりも極端な形でそうした課題が現れた。
でも、だからこそ、ここで挑戦することは人生にとって貴重な経験となるはずだ。

「小高には新たなチャレンジを始めている若者がたくさんいて、コミュニティができあがっています。自分で何かやりたいとか、課題解決に取り組みたいと考えている若い世代にとって、小高はとてもいい環境だと思います。」
「東京にいると競合が多かったり、場所がなかったりしてできないことでも、小高であれば挑戦できます。自分×小高で、他に替えの効かない、その人だからできる仕事が、ここならできるのが素敵だなって思います。」

たしかな意志を持ってこの地に立つ根本さん。そんな根本さんの心の支えになっているのは音楽や芸術だという。
「最近はコロナ禍を反映して作られた曲をよく聞いています。閉塞感や何もできない無力感があるんだけれども、そんな状況から何かしてみようっていうエネルギーを感じられて。小高の状況にもリンクしている気もするんです。すごく力をもらえますね。」
根本さんは今後、大学で学んだことを生かしながら、アートの分野でもプロジェクトをスタートさせる予定なんだとか。
「この地域ではまだまだ本物の表現に触れる機会が少ないので、そうしたものを提供できる側になりたいなと思っています。今はフィルムコミッションの設立に向けて実際に動き始めました。」
「地域には昔から伝わる踊りなど、生活に根付いた表現の手段がありました。でも今では特殊なものになってしまっている。それはなんか違うなと思っていて、人間が本来必要としていた行為を取り戻せたら面白いですよね。」
震災を境に生まれ変わった小高で、新たなスタートを切った根本さん。小高には、意志を持った若者がキラキラと輝きながら暮らせる環境がある。

文…久保田貴大 撮影…アラタケンジ